写真:岡 泰行

長島城の歴史と見どころ
長島城は、木曽・長良・揖斐の三川に囲まれ、東を伊勢湾に向けた中洲の中央に築かれた。古くは伊藤氏がこの地を治め、文明年間(1469–87)には押附・殿名・竹橋の三か所に砦を構えていたという。永禄4年(1561)には服部友定が北畠氏に属して城を修築したと伝わるが、やがて一向宗願証寺が勢力を強め、元亀元年(1570)に伊藤氏を滅ぼして長島を掌握した。願証寺は石山本願寺と呼応して反信長の拠点となり、元亀・天正年間にかけて織田軍との激戦の舞台となった。
信長は三度にわたり長島を攻め、佐久間信盛・柴田勝家・氏家卜全・九鬼嘉隆らを動員したが、初戦では敗退。しかし天正2年(1574)の総攻撃で一向一揆は壊滅し、男女二万人が討たれるという悲劇を残した。以後、滝川一益がこの地を与えられたが、本能寺の変後に失脚し、城は織田信雄の領地となる。天正13年(1585)の地震で崩壊し、のちに豊臣秀次の家臣・吉田修理亮が再建した。
江戸時代には天野・福島・菅沼・松平・増山氏らが城主を務め、とくに松平定政が修築に尽力した。大手門や桝形、太鼓門を整え、城下の道を広げ松を植えたと伝わる。明治5年(1872)に廃城となり、堀は埋め立てられたが、大手門は蓮生寺に移され、今もその姿を伝えている。
長島城の特徴と構造
長島城は、三川の流れを天然の堀とする中洲の要害であった。江戸期の再整備では、松平定政が大手に桝形虎口を設け、太鼓門・水門・櫓を再建したと伝わる。二の丸には米蔵を置き、本丸には書院が設けられた。城外には桑名へ通じる道筋が整えられ、松並木が往来を飾ったという。現在は学校敷地となり市街地化したため遺構はないが、移築された城門が静かに往時を語っている。

長島中部小学校脇に建つ長島城跡の歴史解説板。

本丸南西隅に残る樹齢300年以上の黒松。

大手橋の石垣。出隅部は古く当時の石垣かと思われる。

旧長島城大手門は、明治9年(1876)に蓮生寺の山門として縮小され移築された。桑名市指定文化財となっている。瓦には増山氏の家紋が残る。
参考文献:『日本城郭大系10』(新人物往来社)
長島城の撮影スポット
長島城の写真集
城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、長島城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。長島城の観光情報・アクセス
岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]
1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。
長島城:城ファンたちの記憶
実際に長島城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全4件)。


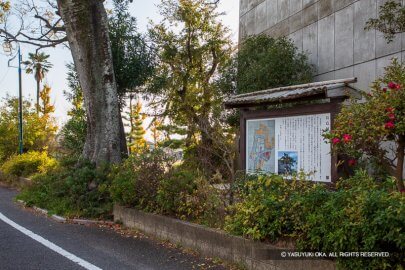









長島中学校の一角に残る「長島の大松」を見上げたとき、ここがかつての本丸跡だったと知った。堀跡をたどり、蓮生寺の大手門へ。いまは静かな町に、あの日の濁流のような歴史が沈んでいる。
( 空蝉日和)
長島城奥書院の居間は深行寺本堂として移築されたと城郭大系などに記載があるが、老朽化のため取り壊され現在は新たに再築されたため、現存はしていないらしい。大手門は蓮生寺表門として残っている。
( こもれうつし)
案内板をたどりながら、長島中部小学校の敷地にある城跡を歩いた。遺構は残らないけれど、蓮生寺の大手門や願証寺の碑を見ると、信長との激戦がここであったことを実感した。
( 風土記のたまご)
三重県長島町にある「輪中の郷」という施設に行ってまいりました。ここは長島町の歴史と輪中、伊勢湾台風について展示しているのですが、ここに、長島城の模型と絵図が展示してあります。この模型は幕末(増山氏2万石)の長島城を再現していていますが、なんども洪水の被害にあったりし、石高が2万石ということもあり、本丸の御殿と大手門周辺以外の施設はあまり整備されていなかったようです。絵図面(多分江戸期のものの写し)も写図ですが、何枚か展示されていました。あと、長島一向一揆の展示やドラマ(市原悦子主演)上映、漫画による一向一揆の説明ビデオもありました。織田信長が悪役に描かれておりました。で、ここは家族で遊びに来ても楽しめます。海苔すき体験ができたり、滑り台、芝生広場なんかの施設があります。
( Haru)