写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

小浜城の歴史と見どころ
若狭湾に面した水運の要衝、小浜。その海辺の平地に築かれた小浜城(おばまじょう)は、江戸時代初頭、京極高次によって築城が始まり、のちに酒井氏の居城として完成をみた。北川と南川という二本の自然河川に挟まれた三角州上に、本丸を起点として二ノ丸・三ノ丸が川に沿って南東方向へと連なる構成は、水運と政務を両立させた巧みな設計であった。いま遺構の多くは失われたが、本丸石垣や天守台が残され、発掘調査により当時の構造が次第に明らかになってきている。静かな風景の中に、城と城下町が重ねた時間が静かに息づいている。
小浜城の歴史
小浜城が築かれたのは、江戸時代初頭のことである。関ヶ原の戦いの功績により若狭一国を与えられた京極高次が、慶長6年(1601)に築城を開始した。それまでの居城は後瀬山城であったが、山上に位置していたため、政務や交通の利便性に欠けていた。これに対し、小浜湾に面し北川と南川に挟まれた平地は、港を擁し城下町の形成にも適した地形であった。
新たな拠点としての小浜城は、京極氏によって基礎が築かれ、その後の城主である酒井忠勝の手によって完成に至る。忠勝は寛永11年(1634)に若狭へ入封し、藩政の拠点を整備した。そして寛永13年(1636)、三層の天守を完成させ、城郭としての姿を整える。天守の高さは約29mに達し、小浜湾を見下ろす姿は、まさに一国の威容を示すものであった。この後、小浜藩は酒井氏14代によって統治されることとなる。以後、およそ238年間にわたって城は藩政の中心として機能し幕末まで続いた。
明治4年(1871)、廃藩置県により小浜藩は廃され、小浜県庁が置かれるが、同年12月、二の丸の建物から出火し、旧城の多くが焼失してしまった。さらに明治7年(1874)には、天守をはじめとする主要な建物も取り壊され、城郭としての姿はほぼ失われることとなる。
現在、本丸跡には小浜神社が建てられ、天守台が静かに往時を伝えている。また、発掘調査により三ノ丸の米蔵跡や大手門跡、京極期の石垣などが次々に確認されており、失われた城郭の姿を少しずつ取り戻しつつある。
小浜城と一体となって発展した城下町「西組」は、今も伝統的な町割りを残し、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。城だけでなく町までもが歴史を伝える空間として、訪れる者に深い印象を与えてくれる。
小浜城の特徴と構造
小浜城は、若狭湾に面した三角州の地形を巧みに活かし、北川と南川という二つの自然河川に挟まれて築かれた平城である。三方を水に囲まれたこの構造は、天然の外堀としての機能を果たすとともに、城と港、そして背後の町場とを結びつける交通の要衝としての性格を備えていた。まさに、防御と流通の両立を意図した、戦略的かつ実用的な立地である。
縄張は南北に長く延びる直線型で、本丸を起点に二ノ丸・三ノ丸が川沿いに配置されている。本丸の西寄りには、かつて三層の天守がそびえていた。現在は失われているものの、天守台が現存しており、その規模と構造の一端を今に伝えている。石垣は精緻に積まれ、海に面する側では波止と接続され、藩の御用船の発着場としても機能していた。
本丸の周囲には高石垣が築かれ、南北の郭には政庁や藩主の御殿、米蔵、門などの施設が置かれていた。発掘調査により、三ノ丸からは建物跡や石段、大手門の痕跡が確認され、また二ノ丸北東部では京極高次期の古い石垣も発見されている。
天守台跡と石垣
本丸西端に位置する天守台には、現在も往時の石垣が静かに佇んでいる。かつてここに建てられていたのは、高さ約29mに及ぶ三層の天守である。天守本体の高さは約18 mで、その台となる石垣を含めると全高約29 mに達していた。海を背にそびえ立つその姿は、小浜湾を行き交う船からも見えたという。石垣は高さ・積み方ともに整い、技巧の高さを示している。
本丸の石垣は、切石と自然石を併用した布積みで構成されており、精緻ながらも野趣を残す積み方が印象的である。特に西側や北側の石垣は高く、約11mに達する場所も確認されており、その量感は天守台の威容と相まって城の中枢性を強く感じさせる。石材には地元産の花崗岩が用いられ、角部には算木積みが施されている。石の面を揃えつつも、自然の形を生かした積み方には、初期江戸期の技術と美意識がうかがえる。
京極期の石垣(二ノ丸北東部)
二ノ丸北東部の発掘調査では、京極高次が築いたころの古い石垣が確認されている。積み方は比較的粗く、後の酒井期に見られる整った積み方とは明らかな違いがあり、野面積みに近い特徴を有する。発掘調査で出土した京極期の石垣は、現在では目にすることはできないが、発掘によって城の成り立ちが丁寧に解き明かされつつある。
三ノ丸の米蔵跡と大手門跡
三ノ丸では発掘調査により、米蔵の礎石や石段、そして大手門の遺構が確認されている。これらの構造は、江戸後期の城絵図と照合して位置や形状が確認されており、今後の復元整備に向けた重要な手がかりともなっている。これらの遺構は現在は見られない。
小浜城下町
小浜城下町は、中州にある小浜城を中心に、南川の対岸に竹原武家屋敷(現在の一番町、千種、四谷、大手など)、北川の対岸に西津武家屋敷(現在の雲浜、山手)を配した。竹原武家屋敷は濠によって重ねて守られており、街道沿いの防御性を高めていた。一方、西津武家屋敷には筋違いの道や桝形が設けられ、敵の侵入を防ぐ構造が今も町並みに残る。いずれの区域も、現在に至るまで町割りが継承され、歴史的景観のなかに城下の暮らしの名残が息づいている。
参考文献:
- 小浜市Webサイト「小浜城跡と城下町の構造」
小浜城の学びに役立つ本と資料
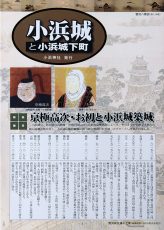 小浜神社拝殿のお賽銭箱の横に、小浜神社発行の『小浜城と小浜城下町』の冊子がある(A4・8ページ・100円)。また、小浜神社鳥居右手に案内板、絵馬堂内部に、小浜城と城下町の絵図がある。
小浜神社拝殿のお賽銭箱の横に、小浜神社発行の『小浜城と小浜城下町』の冊子がある(A4・8ページ・100円)。また、小浜神社鳥居右手に案内板、絵馬堂内部に、小浜城と城下町の絵図がある。
小浜城の撮影スポット
 小浜城跡を訪れたなら、ぜひカメラ片手に歩きたい。現在は小浜神社の境内として静かに残る本丸周辺は、石垣風景を狙いたい。代表的な撮影カットとなるのが、天守台跡を本丸城内側からとらえた構図である。多聞櫓跡と思われる石垣のラインとその雁木(石階段)を前景におさめ、その先に連結する天守台を据えることで、立体的で奥行きのある構図となる。周囲には木々が生い茂り、日差しが強いと影が強調されやすいため、曇天の日に撮影すると、石の質感や苔の表情が柔らかく引き立つ。
小浜城跡を訪れたなら、ぜひカメラ片手に歩きたい。現在は小浜神社の境内として静かに残る本丸周辺は、石垣風景を狙いたい。代表的な撮影カットとなるのが、天守台跡を本丸城内側からとらえた構図である。多聞櫓跡と思われる石垣のラインとその雁木(石階段)を前景におさめ、その先に連結する天守台を据えることで、立体的で奥行きのある構図となる。周囲には木々が生い茂り、日差しが強いと影が強調されやすいため、曇天の日に撮影すると、石の質感や苔の表情が柔らかく引き立つ。
小浜城の周辺史跡を訪ねて
小浜城を訪ね歩くとき、目を凝らせば城外にもその痕跡が息づいている。小浜神社境内の「酒井家邸宅門(縮小移築)」、県立若狭高校正門に残る旧藩校「順造館」の門、そして多田寺に移された書院玄関。それぞれが藩政期の記憶を静かに伝えている。
小浜神社境内の「酒井家邸宅門(縮小移築)」
小浜城本丸跡に鎮座する小浜神社。その鳥居すぐに、かつての藩主酒井家の邸宅門が、縮小移築のかたちで現存している。この門は、明治維新後に城郭の建物が取り壊された際に残された数少ない木造建築のひとつであり、本来は藩主の私的空間である邸宅の玄関口に据えられていたと伝わる格式ある門である。縮小されているとはいえ、切妻屋根や格子の意匠、用いられた材の風格には、旧藩主家の品位が今も漂う。神社参拝の折に、歴史の余香をたたえるこの門に気づけば、小浜城の暮らしの一端が垣間見える。
福井県立若狭高校正門(旧藩校・順造館正門)
現在、福井県立若狭高等学校の正門として使用されている門は、かつて小浜藩の藩校「順造館(じゅんぞうかん)」の正門であった。順造館は、酒井忠進の時代に設けられた藩の教育機関であり、儒学や兵法を中心に、藩士の子弟教育の場として重要な役割を果たしていた。正門は簡素ながら品位を備えた造りで、藩校らしい簡素で落ち着いた意匠は、今も静かな佇まいとして見る者に印象を残す。小浜城の知的中枢ともいえる空間の名残が、現代の学び舎の入口として今も受け継がれていることは、城とまちの歴史的な連続性というものを感じさせてくれる。
多田寺に移築された「小浜城書院玄関」
小浜市多田に所在する天台宗の古刹・多田寺には、小浜城の書院玄関が移築・保存されている。この玄関は、藩主や公用客との対面に用いられたとされる書院の玄関部分であり、格式高い空間の一部であった。移築先の多田寺は、もともと藩主酒井家の信仰厚い寺院でもあり、こうした歴史的背景から書院の一部が保管されることとなった。現在の建物は、玄関部分のみながらも、欄間や框、屋根構造などに当時の意匠を残しており、藩政期の書院建築の一端をうかがうことができる。静かな境内に佇むその姿には、小浜城のかつての生活と礼儀の空気が確かに宿っている。
近隣の主要な城
小浜城の前身は、海を望む後瀬山に築かれた中世山城・後瀬山城である。戦国の気配を色濃く残す国吉城、細川幽斎ゆかりの田辺城、そして港町敦賀の中心に置かれた敦賀城など、小浜を中心とする若狭・丹後一帯には、海陸交通を睨んだ城が点在する。いずれも歴史の層を重ねた構造と、地域を護った記憶を静かにとどめており、小浜城とともに訪ね歩けば、時の流れが立体的に浮かび上がってくる。
小浜城の周辺おすすめ名物料理
若狭の海とともに生きてきた小浜の城下町には、歴史の味が今も息づいている。まず筆頭は、小鯛のささ漬け。酢締めにされた若狭鯛が、笹の香とともに上品に口にひろがる。続いて、鯖街道にその名を刻む焼き鯖寿司。脂ののった鯖が香ばしく、酢飯と調和する一品だ。甘味では、冬の定番である「でっちようかん」も外せない。控えめな甘さが散策の休みに寄り添う。そして漁港に近い店では、新鮮な魚介をふんだんに盛った海鮮丼が、目と舌を満たしてくれる。歴史と海の恵みが、旅の記憶にやさしく残る。
小浜城観光のおすすめホテル
小浜城跡から徒歩約1分の「ビジネスホテル若杉本館」は、駅至近で観光拠点に最適。駅から徒歩約5分の「ビジネスホテル山海」も利便性が良く、周辺飲食店やコンビニにも近い。温泉では、小浜中心域から車で約30分、気山駅近くの虹岳島温泉「虹岳島荘」が、湖畔の源泉かけ流しと地元食材の会席で旅の疲れを癒す。城巡りとともに心地よい夜を過ごすには最適な宿泊地となろう。
小浜城の観光情報・アクセス
所在地
住所:福井県小浜市城内1丁目7-55 [MAP] 県別一覧[福井県]
電話:0770‑64‑6034(小浜市文化観光課)
電話:0770‑52‑1920(小浜神社)
- 小浜城公式サイト(小浜市)
アクセス
鉄道利用
JR小浜線、小浜駅下車、徒歩15分。小浜神社を目指す。レンタサイクルもある。
マイカー利用
舞鶴自動車道舞鶴東IC、国道27号を東へ。小浜神社に無料駐車場(3台)有り。
岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]
1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。
小浜城:城ファンたちの記憶
実際に小浜城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全6件)。












かつては三層の天守を備え、櫓の数は42、門櫓5、多聞10、狭間の数は1320と相当な規模の城だったが、現在は小浜神社のある本丸の一部が残るのみ(天守台あり)。
( shirofan)
付近の城では、後瀬山城。同じ街の中に戦国時代より前の山城の址が残っている。別名武田城。また、小浜のグルメでは「すし政(すしまさ)」寿司屋。JR駅から小浜城址への途中、市役所前。若狭の魚をつかったネタなら何でもOK。
( 藤田茂樹)
譜代大名酒井家12万石の領地であったため、明治初年まで天守も残されていた。小浜市は2004年、城の復元計画を発表し、10年計画をスタートさせた。完成想像図や古写真、募金計画などが紹介されている。
( 藤田茂樹)
毎年5月はじめにお城祭りがあり、酒井忠勝が川越から連れてきたといわれる伝統芸能の獅子舞が奉納されている。小浜藩は、藩医として解体新書を書いた杉田玄白でも有名。
( 藤田茂樹)
天守台を含む本丸部分の石垣だけがかろうじて残っていて、内部は、江戸時代にこの地に川越から転封された酒井忠勝を祀る小浜神社となっている。酒井忠勝は「樅の木はのこった」で有名な伊達騒動のときの大老。
( 藤田茂樹)
もともとは川2つにはさまれたなかなかの水城だったようですが、最近の護岸工事で川の流れが変えられてしまい、旧城跡はほとんどが川の流れに飲まれてしまいました。
( よーすけ)