写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

大溝城の歴史と見どころ
琵琶湖北西の湖畔に築かれた大溝城(おおみぞじょう)は、戦国時代末期に織田信長の甥・織田信澄が築いた水城である。乙女ヶ池を外堀に取り込む構造は、湖上交通の要衝として戦略的な意味を持ち、信澄の家格と将来性を映し出すものであったが、同時に織田政権の琵琶湖支配戦略における要衝としての重要性も色濃く反映されていた。天正10年(1582)、本能寺の変に連座するかたちで信澄は非業の最期を遂げ、城もまたその命運を大きく変えていくこととなる。時を経て城は元和の一国一城令により廃され 、分部氏(わけべし)が2万石で入封し 、その跡地に政庁機能を備えた陣屋町として再出発を遂げた。水と石が語る記憶が、いまも湖辺に息づいている。
大溝城の歴史
大溝城が築かれたのは、織田信長の甥・織田信澄による天正6年(1578)のことだった。城地は琵琶湖北西部の内湖・乙女ヶ池に面した水辺にあり、自然の水域と導水路を巧みに取り込んだ水城として構築された。設計には明智光秀が関わったとされ、その縄張りや城下の整備には、織田政権下での湖上交通を統制する意図が色濃く表れていた。
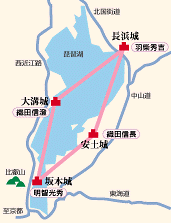 大溝城は、安土城を中心とし、長浜城、坂本城とともに、琵琶湖を囲む織田政権4城ネットワークのひとつだ。
大溝城は、安土城を中心とし、長浜城、坂本城とともに、琵琶湖を囲む織田政権4城ネットワークのひとつだ。
信澄は信長の弟・信行の子にあたり、若くして要地を任されていた。さらに光秀の娘を妻に迎えていたことから、信長の側近として将来を嘱望された存在でもあった。だが天正10年(1582)、本能寺の変が起こり、信長が討たれると、信澄の運命も大きく揺らぐこととなった。
事件当時、信澄は摂津の茨木城に在城していたが、明智光秀の娘婿であるという理由で、光秀に内通していたのではないかという疑いをかけられた。信澄が本能寺の変に関与していた明確な証拠はなく、むしろ行動の詳細は不明のままだったが、政局が極めて不安定となった中で、織田信孝・丹羽長秀らは迅速な対応を選び、信澄は変の2日後、大坂・堺の南宗寺にて自害を命じられ、非業の死を遂げた。冤罪の可能性も指摘されており、変の余波が織田家内部にまで波及した象徴的な出来事といえる。
その後、大溝城は信孝の手を経て、丹羽長秀、加藤光泰、生駒親正、京極高次といった有力大名に引き継がれていった。関ヶ原の戦い後、京極氏が若狭(小浜城)へ転封すると、元和5年(1619)には分部光信が大溝に2万石で入封する。だが、この時点ですでに幕府は「一国一城令」を発しており、分部氏の石高や格式では城郭の維持は認められなかった。
こうして大溝城は廃され、代わって政庁機能を備えた大溝陣屋が整備された。以後、分部氏は12代にわたってこの地を治め、町割と水路の整った陣屋町は、明治維新に至るまで地域の政治と暮らしの中心であり続けた。
現在、本丸跡に残る天守台石垣や、城下町を潤す水路は、往時の構造を今に伝えている。平成27年(2015)には「大溝の水辺景観」が国の重要文化的景観に選定され 、さらに日本遺産「琵琶湖とその水辺景観」の構成資産にも登録された 。戦国の波と江戸の静寂が交わる湖畔に、時の記憶が静かに宿っている。
大溝城の特徴と構造
湖畔に築かれた平城(湖城)としての特色が色濃く、大溝城は琵琶湖から伸びる内湖・乙女ヶ池や導水路を外堀とした水城であった。野面積みによる天守台石垣、本丸跡、さらに城下町へ続く陣屋の惣門と水路が、一体として戦国から江戸期の城郭都市構造を今に留めている。
天守台(本丸南東部)
大溝城の天守台は、本丸の南東隅に位置する。東西24m、南北29m、高さは約5m(最大6.5m)と推定される 。この天守台は、花崗岩を用いた野面積み(自然石を加工せず積み上げる古式の石積技法)で構築されているが、隅部には算木積みが見られる。特に保存状態が良好な西側中央角の石垣で算木積みが確認されており、これは築城当時の高度な技術水準を物語る。算木積みは、石垣の隅部を強度高く築くための先進的な技法であり、織豊系城郭の特徴の一つである。
昭和58年(1983)および平成22年(2010)の発掘調査により、天守台の東側に南北方向へ延びる石垣が検出されている。また、出土した天正期の軒丸瓦・軒平瓦は、安土城出土のものと類似する形式を持つことが指摘されており、当時の主郭建物にこれらの瓦が使用されていた可能性が高い。
これらの遺構は、大溝城が織田政権下の湖上交通支配を担う拠点として、安土城に匹敵する、あるいは共通の築城技術が投入されていたことを如実に示している。安土城は信長の天下統一の象徴であり、その最先端の技術が大溝城にも適用されたことは、大溝城が織田政権の広範な戦略においていかに重要視されていたかを明確に示している。
本丸(主郭部)
大溝城の本丸は、東西約55m、南北約60m、面積約3,300m²を測る、ほぼ方形に近い縄張りを有している。四隅のうち、南東には天守台が構築され、東の端と西の端には櫓台が付けられていたとみられている。防御性と指揮機能を兼ね備えた主郭として整備された本丸は、乙女ヶ池に面していた。
本丸の外郭を囲む石塁は、琵琶湖からの風波の侵入を防ぎ、水害への備えを意図したものと考えられている 。本丸の北端部の石垣には階段状に折れた構造が見られ、ここに船着場が設けられていた可能性が高い。これは、琵琶湖を通じた物資の搬入や緊急連絡の拠点として、水上交通を積極的に利用していたことを示唆しており、城が単なる陸上防御拠点ではなく、琵琶湖という広大な水域を最大限に活用した「水陸両用」の戦略拠点であったことを裏付けている。
また、本丸と二の丸をつなぐ幅約7mの土橋が発掘調査により確認されている。石垣の積み方には、大小の石を巧みに組み合わせ、間に割栗石(間詰石)を丁寧に詰める技法が用いられ、使用された石材は比良山地から切り出され、琵琶湖を筏で運搬されたと伝わっている。このような大規模な石材の運搬は、当時の高度な土木技術と物流能力、そして織田政権の組織力を示すものだ。
乙女ヶ池(水堀)
乙女ヶ池は、大溝城の東側に広がる自然の池であり、かつては城の外堀として重要な役割を果たしていた。築城当時は琵琶湖と水路でつながっており、水運と防御を兼ね備えた湖城の構造の一端をなしていた。この池は、琵琶湖の岸辺に形成された浅く入り組んだ内湖の一部で、もともとは静かな入江のような地形をなしていたものを、天正6年(1578)の築城時に堀として巧みに取り込んだと考えられている。
発掘調査では、乙女ヶ池の南岸に石積や土留めの構造が検出されており、池の一部に人工的な改修が施されていたことが明らかになっている。特に本丸の北側に接続する水際部では、船着き場とみられる構造が見つかっており、水上交通と城の機能が密接に連動していた様子がうかがえる。乙女ヶ池と城内の堀をつなぐ導水路も確認されており、これは平常時の水位管理や防御的な意図のために整備されたと推測される。
こうした自然地形の活用と人工的な改修の組み合わせは、当時の築城技術が自然環境を最大限に利用しつつ、戦略的・機能的な要請に応じて大胆に地形を改変する柔軟性を持っていたことを示している。これは、単なる防御に留まらない、多機能な水城の概念を浮き彫りにするものである。大溝城の構造は、坂本城や安土城など、同時代の水城と共通する特徴を備えており、戦国末期の先進的な築城思想の一端を示している。
現在の乙女ヶ池は、ヨシ原とともに大溝の風景を形づくり、平成27年(2015)に国の重要文化的景観に選定された「大溝の水辺景観」の中核をなしている。
陣屋総門(長屋門)
大溝城が元和5年(1619)に廃城となった後、分部光信が大溝に入封し、旧城跡の一角に新たに大溝陣屋が築かれた 。陣屋は城郭の構造の一部を引き継ぎつつ、藩政の中心地として機能し、以後、明治維新までの約250年間にわたり分部氏の支配が続いた。
この陣屋の表門として現存しているのが「陣屋総門(長屋門)」である 。この門は、入母屋造、瓦葺、三間半幅をもつ堂々たる木造建築で、両脇に長屋部分を付属する形式が特徴的である。屋根瓦には分部家の家紋である「隅立て四つ目結」が据えられ 、大名家としての格式と誇りを伝えている。
陣屋総門は、平成16年(2004)に高島市の有形文化財に指定された 。この門は、宝暦5年(1755)の大改修を経て、近年まで民家として使われていたが、高島市が買い上げ、文化財として管理されている 。近年、復原整備工事が完了し、令和6年(2024)4月1日にオープンした 。大溝城のCG映像なども放映され「大溝まち並み案内処」として活用されている。
参考文献:
- 『広報たかしま 2015年11月号 大溝城と水口岡山城』(高島市)
- 『広報たかしま 2017年4月号 大溝城遺跡の発掘調査』(高島市)
- 『大溝藩と分部氏〜城下町の400年』(2018年11月 大溝の水辺景観まちづくり協議会)
- 高島市Webサイト「大溝城跡と城下町」「大溝陣屋総門」
- Webサイト「国指定文化財等データベース 大溝の水辺景観」(文化庁)
大溝城の学びに役立つ本と資料
- 『織田信澄と大溝城』(モノクロB5二つ折り)
- 平成27年12月に行われた『大溝城遺跡 発掘調査現地説明会資料』(カラーA3二つ折り)
- 『大溝陣屋遺跡』(カラーA4両面)
- 『近江高島・大溝の水辺さんぽ』(カラー三つ折りパンフレット)
そのほか、大溝陣屋の惣門に行けば、いろいろと資料がある。
大溝城の散策コース
大溝城は初めて訪れると近江高島駅から大溝城の城跡までの道のりが分かりにくいため事前に、ルートをチェックしておくと良い。天守台を見た後は、唯一、現存する大溝藩の建築物、武家と町人の町を区切る大溝陣屋の惣門や、町割り水路など、大溝城とともにその城下町の散策を。
大溝城までの道のり
 近江高島駅から、大溝城の城跡までの道が分かりにくいので事前に要チェック。駅の売店付近に、大溝城へのアクセスマップが貼られている。駅前の通りを東へ進み、最初の信号(近江高島駅口交差点)を右へ進んだところ右手に、三の丸跡を示す石碑があり、その脇から城跡への小道がある。写真はその入口(詳しくはGoogleマップ参照)。
近江高島駅から、大溝城の城跡までの道が分かりにくいので事前に要チェック。駅の売店付近に、大溝城へのアクセスマップが貼られている。駅前の通りを東へ進み、最初の信号(近江高島駅口交差点)を右へ進んだところ右手に、三の丸跡を示す石碑があり、その脇から城跡への小道がある。写真はその入口(詳しくはGoogleマップ参照)。
大溝城の撮影スポット
大溝城を訪ねるなら、かつての構造をいまに伝える「痕跡」を丁寧におさえておきたい。以下は、最低限記録しておきたい3つの撮影対象だ。
天守台は、野面積みの石が力強く積み上がる迫力ある構造となっている。隅部の算木積みは、当時の築城技術の高さを物語る意匠であり、アングル内に必ず収めたい。天守台の顔といっていい場所は南向きのため、順光で石の荒々しさを写し込むと良い。
また、本丸の南東に広がる「乙女ヶ池」は、もともと琵琶湖の内湖として存在し、外堀として巧みに取り込まれた天然の防御線だった。現在も湿地と池が残り、湖城の面影を色濃く残す風景が広がっている。本丸から池を望むには順光となる午後が狙い目となる。
「大溝陣屋総門」は、江戸期に分部氏が整備した陣屋の惣門であり、現存する数少ない建築遺構の一つとなっている。城下町の正面玄関としての存在感も際立ち、門は北向きであるため、朝夕に正面から撮ると光が柔らかく回り、屋根の陰影が美しく映る。屋根瓦にあしらわれた分部家の家紋(隅立て四つ目結)も望遠で切り取っておきたい。門の両脇に連なる長屋部分を画面内に収めることで、建築の構造的な魅力が際立つ。
大溝城の写真集
城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、大溝城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。大溝城の周辺史跡を訪ねて
武家と町人の町を区切る大溝陣屋の惣門
 織田時代の大溝城の建築物ではないが、唯一、現存する大溝藩の建築物で、高島市指定文化財。伊賀上野から入封した分部光信は大溝城の西に陣屋や武家屋敷を作り、町人地との境に、正面玄関として惣門が作られた。いわゆる長屋門で、入母屋には分部氏の紋が使われた瓦がある。内部は資料などが閲覧できる町並み案内所となっており大溝の歴史が分かる。武家エリアの西側には、藩校脩身堂跡石碑がある(詳しい場所はGoogleマップ参照)。
織田時代の大溝城の建築物ではないが、唯一、現存する大溝藩の建築物で、高島市指定文化財。伊賀上野から入封した分部光信は大溝城の西に陣屋や武家屋敷を作り、町人地との境に、正面玄関として惣門が作られた。いわゆる長屋門で、入母屋には分部氏の紋が使われた瓦がある。内部は資料などが閲覧できる町並み案内所となっており大溝の歴史が分かる。武家エリアの西側には、藩校脩身堂跡石碑がある(詳しい場所はGoogleマップ参照)。
大溝の町割り水路
 大溝陣屋の城下町には、通りの中央に水路を通した町割り水路が3カ所に残る。当時は国道161号線下にもあって(現在は暗渠に)計4本だったらしい。近年ではあまり残っていないが、大和郡山城の城下でもこういった水路が見られる。
大溝陣屋の城下町には、通りの中央に水路を通した町割り水路が3カ所に残る。当時は国道161号線下にもあって(現在は暗渠に)計4本だったらしい。近年ではあまり残っていないが、大和郡山城の城下でもこういった水路が見られる。
水路は道路の中央に沿って流れ、その両側に町家や武家屋敷が並ぶ構造となっている。水を道とともに配置する形式は、同市新旭町の針江地区などで見られる「川端(かわばた)」と呼ばれる水利用文化とも通じるが、大溝城下でその名称が用いられていたかは定かではない。ただ、水との共生を軸とした町づくりという点では、同様の思想が息づいていたといえる。
平成27年(2015)には、この町割り水路と周辺景観が「大溝の水辺景観」として国の重要文化的景観に選定された。今もなお水が流れ、石橋が架かるこの風景は、時代を越えて人々の暮らしに寄り添い続けている。
大溝城の移築書院
勝安寺本堂は、大溝城本丸に建てられていた書院(御殿)が後に移築されたものと伝わる。
大溝藩主分部家墓所
 圓光禪寺に霊廟があり、初代(光信は京都の大徳寺)、七代以外の歴代藩主の墓がある。圓光禪寺は、分武家が伊賀上野時代からの菩提寺で、元和5年(1619)、大溝へ国替えとなり、圓光禪寺が大溝にも建立された(詳しい場所はGoogleマップ参照)。
圓光禪寺に霊廟があり、初代(光信は京都の大徳寺)、七代以外の歴代藩主の墓がある。圓光禪寺は、分武家が伊賀上野時代からの菩提寺で、元和5年(1619)、大溝へ国替えとなり、圓光禪寺が大溝にも建立された(詳しい場所はGoogleマップ参照)。
近藤重蔵、謫居跡
 近藤重蔵は、伊能忠敬とともに、地図を完成させるため蝦夷(北海道)や、エトロフ島まで踏破した探検家。江戸城内で御書物奉行を務めたが、息子が事件を起こし大溝藩で謫居することになる。その謫居跡の石碑が惣門近くの駐車場脇にある。墓は圓光禪寺の塔頭のひとつ、瑞雪禅院の裏山にある(高島市指定史跡)。
近藤重蔵は、伊能忠敬とともに、地図を完成させるため蝦夷(北海道)や、エトロフ島まで踏破した探検家。江戸城内で御書物奉行を務めたが、息子が事件を起こし大溝藩で謫居することになる。その謫居跡の石碑が惣門近くの駐車場脇にある。墓は圓光禪寺の塔頭のひとつ、瑞雪禅院の裏山にある(高島市指定史跡)。
付近の有名城
付近の有名城といえば、明智光秀の坂本城。
大溝城観光のおすすめホテル
この辺りに宿泊できるところは無い。大溝城址のみだと必要な時間は15分程度のため、旅の通過点とすべし。
大溝城の観光情報・アクセス
所在地
住所:滋賀県高島郡高島町勝野 [MAP] 県別一覧[滋賀県]
電話:0740‑25‑8559(高島市文化財課(大溝城跡))
電話:0740‑36‑2011(大溝陣屋 総門(案内施設))
- 大溝城跡(高島市)
アクセス
鉄道利用
JR湖西線、近江高島駅下車、徒歩5分。高島市民病院(二の丸跡)の東側が本丸跡で天守台が残っている(徒歩ルートはGoogleマップ参照)。
マイカー利用
名神高速道路、京都東ICから国道161号線を北上、近江高島駅を目指す。約40分(43km)。駅西側の有料駐車場を利用する(近江高島駅前第1駐車場・31台)。
大溝城天守台、大溝陣屋の惣門や町割り水路などの散策は、駐車場が無いため駅前駐車場に駐めて、徒歩散策が良い。大溝藩主分部家墓所のある圓光禪寺は駐車場有り。
岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]
1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。
大溝城:城ファンたちの記憶
実際に大溝城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全7件)。












2018年3月、高島市教育委員会が江戸時代の絵図『大溝城下古図』をもとに発掘を行い、本丸の北側と南側で高さ約1mの石垣や瓦が見つかったそう。廃城時に石垣を壊した痕跡も確認された。工法から天正期の築城当時のものなのだとか。
( 城好きの匿名希望)
2015年12月、発掘調査で大溝城に船着き場らしき石垣の遺構が見つかったらしい。船から直接本丸に上がれる構造だったのかもしれないとのこと。
( shirofan)
この地は古くから北陸と京都を結ぶ最短距離であり、湖と山は平野くぎり街道を遮断していることから戦略上の要所であることがわかる。遺構は天守台石垣が残るのみである。
( 半兵衛)
近江高島駅から、駅前の通りを南下すると最初の三叉路の交差点の右側に、三の丸跡を示す石碑がある。
( 半兵衛)
壬申の乱(672)に落城した三尾城が背後の三尾山山中にあったという。(「日本書記」天武紀)
( 光秀)
本丸跡から安土城と同じ軒丸瓦1類・軒丸瓦2類・丸瓦が出土。(高島町教育委員会 s58)
( 光秀)
大溝城の詳細は明らかではないが、「織田城郭絵図面」によると本丸は堀で囲まれており、堀にそって侍町通りがめぐっている。
その通り沿いには信澄の家臣と思われる21の姓が記されており、その中には近江の佐々木氏の同族の高島郡を治めていた”高島七頭”のうちの2人、朽木氏や永田氏の名もある。
( 半兵衛)