写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

坂本城の歴史と見どころ
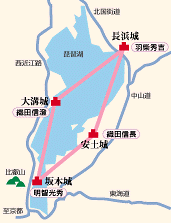 坂本城は、明智光秀の城として有名だ。「幻の城」ともいわれ、その姿が明らかになっていない。城は琵琶湖の南湖西岸にある。西は比叡山が迫り、東は本丸が琵琶湖に面した水城だ。交通の要衝に建ち、信長政権下で安土城、長浜城、大溝城と湖上交通網の一角を担い、京に繋がる港町として繁栄した。
坂本城は、明智光秀の城として有名だ。「幻の城」ともいわれ、その姿が明らかになっていない。城は琵琶湖の南湖西岸にある。西は比叡山が迫り、東は本丸が琵琶湖に面した水城だ。交通の要衝に建ち、信長政権下で安土城、長浜城、大溝城と湖上交通網の一角を担い、京に繋がる港町として繁栄した。
元亀2年(1571)、比叡山焼き討ちの直後に織田信長の命により宇佐山城の明智光秀が坂本城を築いた。天正10年(1582)、本能寺の変に至るまで、光秀の居城となった。その規模は大天守と小天守を有し、ポルトガル宣教師ルイス・フロイスは著書『日本史』で「それは日本人にとって豪壮華麗なもので信長が安土に建てたものにつぎ、この明智の城ほど有名なものは天下にないほどであった」と記している。
天正10年(1582)、明智光秀は山崎の戦いで最期を遂げる。この時、安土城を守っていた明智秀満は、敗北の知らせを受け坂本城に戻るも自害し坂本城は焼け落ちたと伝わる。その後は、羽柴秀吉が城主となり、丹羽長秀が配され城を再建、のちに杉原家次、浅野長政が入った。天正14年(1586)、城と城下町は大津へ移転、資材も移築され、築城から約15年で坂本城は廃城となった。
昭和54年(1979)〜57年、大津市教育委員会により本丸推定地で発掘調査がなされ、約10〜20cmの焼土層や、礎石建物、石組溝、石組井戸などが見つかった。そのすぐ東の琵琶湖の水中には、本丸石垣の一部が残されており、平成6年(1994)には琵琶湖渇水時に石垣の石列が約20mにわたって姿を現している。その後も城域と推定される範囲で数カ所、発掘調査がなされるも、坂本城の外郭というべき三の丸の推定範囲内で城の遺構が見つからず、その全体像は明らかになっていなかった。
坂本城三の丸跡で長さ約30mの石垣を発見
令和6年(2024)2月、民間宅地開発に伴う発掘調査で、住宅地の道路になる部分を発掘、三の丸のものと推定される高さ1m長さ30mの石垣が発見された。この発見は奇跡と言っていい。大津市教育委員会によると、石垣に次の特徴がある。石材は花崗岩で比叡山から採石された自然石を積み上げた野面積み。一部で五輪塔や石塔の転用石が見られた。

根石の下には地盤沈下を防ぐ胴木がなく、裏込め石の幅は狭く、石垣の高さは残り2〜3段ではないかと考えられている。発掘した堀底が泥で水が湧くため、石垣に面した堀は水堀で、堀幅はおそらくは12mほどではないかとしている(発掘範囲は幅約8m)。

石垣の城内側に、幅1mほどの溝が石垣に沿って検出されたが、他に類例がなく、その用途は解っていない。

舟入と推定される石積みが東西方向にあり、こちらには一部に胴木が見られる。
このほか深さ1m60cmほどの石組井戸や礎石建物、瓦などが出土している。織豊期城郭の特徴には、石垣、礎石建物、瓦の出土が挙げられ、今回の調査成果ではそれを満たしており、坂本城の遺構であることが極めて高いとしている。瓦の出土量が本丸跡より少ないことから、三の丸の家臣団屋敷地の一部と考えられている。
さらに大津市教育委員会によると、発掘された三の丸地表面は、本丸の遺構面の高さとほぼ同じで城内の高低差は無い。堀底は、東京湾平均海面(Tokyo Peil:T.P.)から84.6m、琵琶湖の基準水位は84.3mなので、30cmほど外堀の方が高い位置にあるらしい。琵琶湖より高いところが堀底となっているということは、琵琶湖に水を流すかたちになっていたのではないかとしている。
坂本城は江戸時代には場所が分からなくなった。それほど痕跡が無かった。三の丸石垣の出土地も江戸時代から現在まで田畑となっていた場所だ。2024年の調査で、石垣から湖までの距離は約300m、これまで推定されていた南端外郭より約100m小さいことが分かり、また一歩、その姿に近づいたことになる。引き続き今後の発見と調査に期待したい。
参考文献:『明智光秀と戦国時代の大津』(大津市歴史博物館)、2024年2月現地説明会資料(大津市教育委員会)、『日本城郭大系11』(新人物往来社)
三の丸石垣の保存と史跡指定への動き
-
三の丸石垣と外堀跡について宅地造成工事を中止し、大津市と事業者との間で保存する方向で大筋合意に至った。大津市は予定地全体の発掘調査を行い、坂本城跡の国史跡指定を目指す方針。 -
新たに外堀の石垣が発見され、外堀の幅が9mと明らかになった。 -
大津市と京都橘大学による琵琶湖水中調査の成果が発表され、石列が約150mにわたって確認された。坂本城と琵琶湖の境目に防波堤や着岸施設があった可能性が指摘されている。 -
石垣の遺構が見つかった三の丸跡と本丸跡の湖岸が、新たに国の史跡に指定される見込みとなった。
坂本城の学びに役立つ本と資料
大津市歴史博物館で坂本城出土瓦など展示
大津市歴史博物館で、坂本城の発掘調査で出土した鬼瓦や鯱瓦、湖中の石垣位置や江戸時代の坂本などの展示がされており理解を深めることができるぞ。同博物館で『明智光秀と戦国時代の大津』などの図録もGETできる。
坂本城の散策コース
坂本城の痕跡、現地で訪れる場所
坂本を訪れるなら、最低でも「坂本城址公園」「坂本城址石碑二ノ丸跡」「西教寺」「聖衆来迎寺」は訪れておきたい。プラス、琵琶湖の水位が低ければ湖水に沈む本丸石垣を。
 本丸跡は、坂本城址公園の北にあるキーエンス社の保養所(※)の沖で坂本城址公園は城外にあたるのだが、明智光秀の石像、説明板があり、琵琶湖に面した風景が見られる。その本丸跡は湖底に石垣が沈んでおり、普段は水面下のため見られない。過去に琵琶湖の水位が下がり見られた時期があったが、今は琵琶湖の水位が管理調整されており、再びその規模で見られることはないのだが、水位がマイナス50cmほどになると、多少の石列が見られる(詳しくは、下記「撮影方法」の項目を参照)。
本丸跡は、坂本城址公園の北にあるキーエンス社の保養所(※)の沖で坂本城址公園は城外にあたるのだが、明智光秀の石像、説明板があり、琵琶湖に面した風景が見られる。その本丸跡は湖底に石垣が沈んでおり、普段は水面下のため見られない。過去に琵琶湖の水位が下がり見られた時期があったが、今は琵琶湖の水位が管理調整されており、再びその規模で見られることはないのだが、水位がマイナス50cmほどになると、多少の石列が見られる(詳しくは、下記「撮影方法」の項目を参照)。
※2021年11月に再訪するとキーエンス社の表札が無く現在の土地所有者は分からない。
坂本城の撮影スポット
坂本城址公園は実は城外と推定されていて、本丸跡は150m北にある。キーエンス社の保養所跡の沖に桟橋があり、その付近の湖底に石垣がある。平成6年(1994)、平成12年(2000)の琵琶湖渇水時に本丸石垣の根石部分や舟入跡が琵琶湖から現れた。それ以降、琵琶湖の水位が管理調整されており、再びその時の規模で見られることはない。だが雨量によっては、琵琶湖の水位、マイナス50cm前後で、本丸石垣の多少の石列(根石)が写真のように水面に顔を出すことがまれにある。
要するに、本丸石垣の石列を見ようとすると、琵琶湖の水位情報をチェックしてから行くと良い(本丸石垣の詳しい場所はGoogleマップ参照)。2019度の琵琶湖水位曲線を見ると、12月のみマイナス50cmとなっていたが、毎年12月にこうなるという訳ではない。なお、マイナス40cmだと一応は石列がちらりと見える程度なので、できるだけマイナス50cm以上を狙いたい。写真撮影はもしチャンスがあれば、坂本城の歴史をちらっと頭に描いて、夕暮れ時に撮るとどこか悲しげで歴史を感じる絵になるかもしれないぞ。
坂本城の写真集
城郭カメラマンが撮影した「お城めぐりFAN LIBRARY」には、坂本城の魅力を映す写真が並ぶ。事前に目にしておけば現地での発見が鮮やかになり、旅の余韻もいっそう深まる。坂本城の周辺史跡を訪ねて
西教寺の見どころ
 坂本の町外れにある西教寺という大きなお寺は、光秀ゆかりで、書状など様々な関連文書類があります。命日には寺に事務局がある光秀公顕彰会によって法要が営まれている。
坂本の町外れにある西教寺という大きなお寺は、光秀ゆかりで、書状など様々な関連文書類があります。命日には寺に事務局がある光秀公顕彰会によって法要が営まれている。
 西教寺には、坂本城の移築城門、伏見城遺構と伝わる客殿、明智光秀とその一族の墓、細川ガラシャの母、煕子の墓がある。そのほか、境内には、前田利家の六女、前田菊子の墓や、伏見城旧殿を西教寺に移築した山中山城守橘長後の墓もある。ちなみに墓関連では、国道161号線沿い下坂本3丁目の個人宅に、明智塚(明智一族の墓ともいわれている)がある。坂本城の移築城門は来迎寺に、盛安寺には陣太鼓がある(詳しくは上記Googleマップ参照)。
西教寺には、坂本城の移築城門、伏見城遺構と伝わる客殿、明智光秀とその一族の墓、細川ガラシャの母、煕子の墓がある。そのほか、境内には、前田利家の六女、前田菊子の墓や、伏見城旧殿を西教寺に移築した山中山城守橘長後の墓もある。ちなみに墓関連では、国道161号線沿い下坂本3丁目の個人宅に、明智塚(明智一族の墓ともいわれている)がある。坂本城の移築城門は来迎寺に、盛安寺には陣太鼓がある(詳しくは上記Googleマップ参照)。
坂本城の表門と森可成の墓
 聖衆来迎寺(しょうじゅらいこうじ)には、坂本城の表門(重要文化財)が移築現存しており、境内には森可成の墓がある。元亀元年の坂本合戦の時、来迎寺の住職が浅井・朝倉軍のであふれる戦場から、森可成の遺骸を運び弔った。これにより、その後の比叡山焼き討ちから、まぬがれたと伝わっている。
聖衆来迎寺(しょうじゅらいこうじ)には、坂本城の表門(重要文化財)が移築現存しており、境内には森可成の墓がある。元亀元年の坂本合戦の時、来迎寺の住職が浅井・朝倉軍のであふれる戦場から、森可成の遺骸を運び弔った。これにより、その後の比叡山焼き討ちから、まぬがれたと伝わっている。
穴太衆石垣の道
 坂本には「穴太町」という地名が残っている。そう、ここ坂本があの穴太衆の本拠だったところだ。坂本城跡には、若干の石垣が残るのみだが、日吉大社の方に行けば、あるわあるわ石垣。石垣がきれいな町として知られているのがうなずける。坂本城跡で(遺構が何もなく)ストレスを感じたら日吉大社の方へ。JR比叡山坂本駅から山手に登る日吉大社まで続く穴太衆石垣の道が実に風情があって良い。大小を組み合わせた石と白土壁の調和が美しい。ちょうどその道ぞい、京阪石山坂本駅近くに観光案内所があり、ここで坂本の観光地図をGETできる。坂本城の移築城門や光秀の墓、秀吉寄進の石橋の場所などもここで。「そんなことより、そこの湧き水のんでいきなはれ」と言われ、東本宮の向かって左の湧き水を飲む、おいしい。
坂本には「穴太町」という地名が残っている。そう、ここ坂本があの穴太衆の本拠だったところだ。坂本城跡には、若干の石垣が残るのみだが、日吉大社の方に行けば、あるわあるわ石垣。石垣がきれいな町として知られているのがうなずける。坂本城跡で(遺構が何もなく)ストレスを感じたら日吉大社の方へ。JR比叡山坂本駅から山手に登る日吉大社まで続く穴太衆石垣の道が実に風情があって良い。大小を組み合わせた石と白土壁の調和が美しい。ちょうどその道ぞい、京阪石山坂本駅近くに観光案内所があり、ここで坂本の観光地図をGETできる。坂本城の移築城門や光秀の墓、秀吉寄進の石橋の場所などもここで。「そんなことより、そこの湧き水のんでいきなはれ」と言われ、東本宮の向かって左の湧き水を飲む、おいしい。
比叡山延暦寺もすぐ
 また、ここまで来れば比叡山延暦寺。また、日吉大社に足をのばせば日吉三橋(天正年間、秀吉の寄進による国内最古の石橋)がある。京阪石山坂本駅近くの観光案内所でマップをGET。比叡山延暦寺へはケーブルカーで。
また、ここまで来れば比叡山延暦寺。また、日吉大社に足をのばせば日吉三橋(天正年間、秀吉の寄進による国内最古の石橋)がある。京阪石山坂本駅近くの観光案内所でマップをGET。比叡山延暦寺へはケーブルカーで。
余談ながら、延暦寺の発掘調査で、信長の焼き討ちを示す焼土は極めて少なく、本当に焼き討ちがあったかどうか疑問らしい。
また、日光東照宮は「見ざる、言わざる、聞かざる」で有名だが、比叡山延暦寺では「見ざる、聞かざる、言わざる、思わざる」といった具合に最後に「思わざる」が付く。本堂(秀吉が再建)に安置されている猿の像で「見ず聞かず言わざる三つのさるよりも、思わざるこそまさるなりけれ」という意味の4匹目。2016年は年内公開されている。
余談ながら、比叡山延暦寺の根本中堂に、1200年間、灯りが保たれている法灯がある。この灯りを絶やさないよう、毎日、油が注ぎ足されている。これが一説には「油断大敵」の語源とされている(織田信長による比叡山焼き討ちの時、この灯りがそれ以前に立石寺(山形県)に分燈されており、断火を逃れている)。
付近の城
城では、穴太町に壷笠山城跡がある。元亀元年(1570)に浅井・朝倉連合軍が信長軍を相手にたてこもった山城。石垣の遺構あり(京阪石坂線穴太駅下車、山手へ湖の美が丘経由、徒歩40分)。または宇佐山城。そのほか、有名な城では、大津城、膳所城へどうぞ。
明智光秀の首塚や胴塚は京都に
 明智光秀関連でいえば、山崎合戦のとき、光秀は勝竜寺城から逃走することになる。勝竜寺城とここ坂本城をむすぶと、ざっくり中間地点あたりに命を落としたと伝わる「明智薮」がある(京都市伏見区小栗栖小阪町)。この時、家臣が明智光秀の首を埋葬し「首塚」「明智祠」がある(京都市東山区梅宮町)。また、明智藪にほど近い御所内町には「胴塚」がある(京都市山科区勧修寺御所内町)。光秀ファンは見ておきたい(詳しい場所は上記Googleマップ参照)。
明智光秀関連でいえば、山崎合戦のとき、光秀は勝竜寺城から逃走することになる。勝竜寺城とここ坂本城をむすぶと、ざっくり中間地点あたりに命を落としたと伝わる「明智薮」がある(京都市伏見区小栗栖小阪町)。この時、家臣が明智光秀の首を埋葬し「首塚」「明智祠」がある(京都市東山区梅宮町)。また、明智藪にほど近い御所内町には「胴塚」がある(京都市山科区勧修寺御所内町)。光秀ファンは見ておきたい(詳しい場所は上記Googleマップ参照)。
坂本城の周辺おすすめ名物料理
坂本城の観光情報・アクセス
所在地
電話:077-578-6565(坂本観光案内所)
アクセス
鉄道利用
京阪石山坂本線、浜大津駅下車、江若バス監田方面行き15分「石川町」降車、湖岸を徒歩10分。または、JR湖西線、比叡山坂本駅下車、徒歩30分。タクシーあり。
マイカー利用
名神高速道路、京都東ICから国道161号線(西大津バイパス)を北上、約20分。坂本城址公園に10台ほどの無料駐車場がある。明智塚など点在するポイントへは公園駐車場に駐めて徒歩散策が良い。
岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]
1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。
坂本城:城ファンたちの記憶
実際に坂本城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全15件)。
















坂本城本丸跡にあたるキーエンス社の保養所の駐車場が、2020年3月8日から2021年2月7日まで開放、一般公開された時期があった。つまり、坂本城本丸跡から琵琶湖を望むことができる。琵琶湖の水位次第で、坂本城の石列を、水面上から見ることができるかもしれない。キーエンス社の敷地(駐車場)に入ることができるのは、土日祝のみ。時間は9時〜17時。
( shirofan)
現在、滋賀県大津市の大津市埋蔵文化財調査センターで、坂本城跡・大津城跡・膳所城跡の出土遺物が展示されています。
( kinsan)
大津城、坂本城、瀬田城とともに「琵琶湖の浮城」と呼ばれているらしい。ちなみに日本三大湖城は、松江城、膳所城、高島城。
( 光秀)
坂本城は完全な水城で、中心の本丸跡は公園のところではなく、公園の北約100m、キーエンス保養所沖7mにあります。琵琶湖水位が62cmで一列ですが石積みが確認できます。発掘調査は昭和56年に行われ、5階層からなる遺跡だったそうです。光秀以前、光秀時代、丹羽長秀時代、杉原家次時代、浅野長政時代の遺物が発掘されています。現存する公園地は、日吉山王祭で湖上へ御輿を船積みする七本柳という舟入跡です、国道161号線建設で後から作られた船止めで公園北の東南寺川が外堀と言われていますが、当時は城内であったと思われます。
( こうたろう)
坂本龍馬をご存じですか?彼の先祖は明智の落ち武者だったらしいです。山崎の戦いで負けた先祖は、高知県まで落ち延びたそうです。一つの見方としては、龍馬の家紋は“升に桔梗”ですが、これは明智の家紋に由来しているそうです。そして、もちろん龍馬の名字である“坂本”は、この坂本城を文字ってつけたということです。
( 左近)
坂本城が1582(天正10)年に落城した際、天守閣から明智軍武将らが城内にあった金や財宝を琵琶湖へ投棄したという伝説がある。琵琶湖には明智の軍資金が今でも湖底深くに沈んでいる可能性が高い!?
( imex trades co)
碑はいくつかあるようです。まず、湖岸の石碑のそばには光秀の像があります。また、この石碑から200メートルほど北の湖岸が、大渇水時に湖中から石垣が見つかった場所です。さらに300メートルほど北に行くと、東南寺というお寺があり、その前にも「坂本城跡」の碑が建っています。昔、このあたりで城の遺構が発掘されています。本堂東側には明智一族と家来の首塚があり、少し来たには光秀秘蔵の名刀を埋めたという明智塚というのもあるそうです。
( 辻本)
公園の前の琵琶湖の湖底に石垣が残っており、1994年の大渇水で水位が1メートル以上下がったときに姿を現しました。普段は見えないと思います。
( 辻本)
最近になって坂本城跡を公園にしたようだ。きれいでかわいい光秀が立っている。せまいスペースだが、像と石碑、石垣の遺構がある。駐車場も。
( 明智光秀)
坂本は、比叡山、穴太積みの石垣、日吉大社と有名だが、地元の人にとって明智光秀はさほどのウエイトをしめていないのだろうか。城をメインに取り扱ったチラシすらない。
( 明智光秀)
坂本は、中世には人口2万人を超えたと言われて、京・堺に次ぐ大きな町だったらしい。比叡山の表参道の現在は、石垣をめぐらした里坊がつづく静かな町並み。
( shirofan)
この地は古くから北陸と京都を結ぶ最短距離であり、湖と山は平野くぎり街道を遮断していることから戦略上の要所であることがわかる。
( 明智光秀)
穴太衆石垣の道と呼ばれる道には、穴太積みに関しての看板がある。
看板によると、「穴太積みは、自然の石を○○せずに積み上げるものです。」とある。なるほど。さて、○○には何が入る!?
( 半兵衛)
穴太衆は、古くから南坂本を本拠にした石工集団。比叡山の発達とともに繁栄。戦国時代に入り、織田信長の安土城にはじめて用いられ、その後は城郭をメインにする。江戸時代になると穴太頭として幕府に任えることになり最盛期には9人の穴太頭に下に300人をこえ、諸大名のおかかえになる者もいたらしい。現在では大津市の無形文化財技術保持者のある方が、坂本で穴太積みの技術を継承し、全国の城などの石垣修理を手がけているとのこと。
( 半兵衛)
下坂本3丁目には、明智塚(明智一族の墓ともいわれている)がある。坂本城の城内に位置するらしい。余談ですが、皆さん高野山の明智光秀の墓をご覧になったことは、あるでしょうか?小さな五輪の塔なのですが、なんとその中央部にビシッとヒビが入ってます。おそろしや〜おそろしや〜…高野山に行ったときにはお探しを。
( 半兵衛)