写真・記録:岡 泰行/城郭カメラマン

水口岡山城の歴史と見どころ
近江・甲賀の要衝、大岡山(古城山)の麓にそびえる水口岡山城(みなくちおかやまじょう)の歴史は、秀吉から家光へと受け継がれる物語を今に伝えている。
豊臣秀吉は天正13年(1585)、甲賀郡と蒲生郡の支配を固めるため、家臣・中村一氏に大岡山への築城を命じた。標高282 mの丘陵は鈴鹿峠や東海道を眼下に見渡す軍事・交通の要衝であり、山頂には石垣を巡らせ、瓦葺の建物群が立ち並ぶ堂々たる織豊系城郭が築かれた。城下では水口宿の基礎が形作られたとされ、これにより甲賀地域支配の拠点が確立された。同時期、増田長盛・長束正家といった五奉行が城主となり、城の重要性を裏付けている。
慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いでは、長束正家が西軍に属した結果、水口岡山城は池田長吉らの攻撃により炎上、落城・廃城となった。その後、城の石材は江戸時代、水口城(みなくちじょう)に転用されることになる。
廃城後、山麓に整備された城下町との関係は薄れたが、寛永11年(1634)、三代将軍・徳川家光の上洛に伴い、水口城が城山の麓に築かれた。本丸・二の丸を備えた平城であり、作事奉行には小堀遠州らが関与。石垣や水堀を含む豪壮な御殿群は、二条城を模した豪華な造営であったが、家光の泊まりは一度限りとされた。
水口城はその後、水口藩(藩主・加藤氏2万5千石)の藩庁として機能し、加藤明友の時代には「碧水城」とも称された。明治維新後の廃城により建物は失われるも、乾矢倉は資料館として復元され、城跡は水口高校の運動場や史跡公園として今に残る。
現地の発掘調査では、頂部に複数の曲輪と石垣が確認され、堀切・竪堀など織豊期の築城技術をよく伝えている。これらは城郭史において大きな価値を持つとされている。豊かな歴史の痕跡は、大岡山の石垣に、城下町の町並みに、そして城跡を歩む静かな足音に映し出されている。
※なお、戦国期の水口岡山城(山城)は、現在の水口城(平城)とは別の位置に存在しており、両者は時代・構造・機能において明確に区別される。
参考文献:
- 甲賀市Webサイト「水口岡山城跡」
水口岡山城の学びに役立つ本と資料
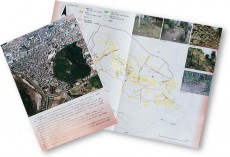 『水口岡山城跡通信』現地の本丸でGET。見どころやが記載された詳細な縄張図となっている。なお、縄張図は現地では、水口小学校側の登山道途中と、本丸に、大きな案内板として設置されている。
『水口岡山城跡通信』現地の本丸でGET。見どころやが記載された詳細な縄張図となっている。なお、縄張図は現地では、水口小学校側の登山道途中と、本丸に、大きな案内板として設置されている。
なお、発掘調査現地説明会資料は、甲賀市のサイトで閲覧できる。
水口岡山城の散策コース
水口岡山城は公園化されており散策自由。比高は100m、山頂の曲輪は整備され、山容に従った形で並び、帯曲輪が取り巻いているのを見ることができる。
水口岡山城の撮影スポット
 近年、発掘調査が行われており、かなり整備されている。本丸西側の石垣も、本丸を取り囲む徒歩ルート「石垣見学コース」ができて整備されて見やすいぞ。城山の全景なら、野洲川の対岸からが良い。
近年、発掘調査が行われており、かなり整備されている。本丸西側の石垣も、本丸を取り囲む徒歩ルート「石垣見学コース」ができて整備されて見やすいぞ。城山の全景なら、野洲川の対岸からが良い。
水口岡山城の周辺史跡を訪ねて
水口岡山城下には、以下の歴史スポットがある。
- 水口城の客殿玄関(移築・蓮華寺)
- 大手枡形推定地と西追手枡形推定地
- 堀跡(用水路がその名残り)
- 徳川家康の腰掛石(大徳寺)
- 近江天保一揆・五倫塔(大徳寺)
- 水口石橋(東海道)
- 東見附跡
- 本陣跡
- 高札場跡
- 人足会所跡
- 問屋場跡
- 善福寺の血天井(水口岡山城が落城した際の血に染まった武士の手形・見学は要事前問い合わせ)
いずれも詳しい場所は、上記Googleマップを参照。 城では、水口城とセットでどうぞ。
水口岡山城の観光情報・アクセス
所在地
住所:滋賀県甲賀市水口町水口 [MAP] 県別一覧[滋賀県]
電話:0748‑69‑2250(甲賀市教育委員会 歴史文化財課)
電話:050‑5491‑1370(一般社団法人 水口岡山城の会)
アクセス
鉄道利用
近江鉄道本線、水口駅下車、国道307号線沿いに徒歩7分(600m)で登山口。
水口城とセットなら、水口城南で降りて水口城を見た後、徒歩で点在する歴史スポットを見ながら、水口岡山城へ行くと良い。
マイカー利用
名神高速道路、竜王ICから国道477号線を南へ約20分(15km)。または新名神高速道路、信楽IC・甲賀ICから約20分(13km)。水口小学校前、登山口下の駐車スペースに駐める。
ちなみに、城山の東側、甲賀市立城山中学校付近からは車道があり、中腹まで車で登ることができる。いずれもほんの数台の駐車スペースしかない。はじめて行くなら前者の水口小学校前からが良いだろう。
岡 泰行 | 城郭カメラマン [プロフィール]
1996年よりWebサイト「お城めぐりFAN」を運営し、日本各地の城郭を訪ね歩いて取材・撮影を続けている。四半世紀にわたる現地経験をもとに、城のたたずまいと風土を記録してきた。撮影を通して美意識を見つめ、遺構や城下町の風景に宿る歴史の息づかいを伝えている。その作品は、書籍・テレビ・新聞など多くのメディアで紹介され、多くの人に城の美しさと文化を伝えている。
水口岡山城:城ファンたちの記憶
実際に水口岡山城を訪れた城ファンの皆さまが綴る、印象に残った景色、人との出会い、歴史メモ、旅のハプニングなど、心に残る旅の記憶を共有しています(全2件)。












水口町の北東に独立した兵陵に秀吉の命により中村一氏によって築かれた。水口岡山城は本丸から三ノ丸にかけて近年の発掘調査により石垣が多数出土した織豊系城郭で関ヶ原の戦いの後、廃城となった。
( 左京)
せっかく水口まで来たんだから古城も行こうということで、古城山まで車を走らせました。山へ登る道があったのでそこを車で登っていくと、遊具公園のような平場に出たので、そこへ車を停め、遊歩道を登ることにしましたが、ほんとに城跡か?と思えるほど城らしい表示はありませんでした。堀切らしいものはありましたが、ほんとにここでいいのかなと思いながら登っていくと、「石垣探訪の道」なる看板が…その道を進むと確かに若干ですが、かつての石垣の遺構がありました。その周辺にも石垣の残石らしきものが転がっていたので、かつては石垣に囲まれていたんでしょうねえ。そこから上に登るとそこが頂上で、どうやら本丸跡のようです。時間がなかったので、ほんと駆け足で回りましたが、お城らしさを感じたのは登り口にあった「岡山城跡」の石柱と説明板、それに堀切、石垣くらいで、現在は市民の憩いの場という感じが強くなっています。
( KUBO)